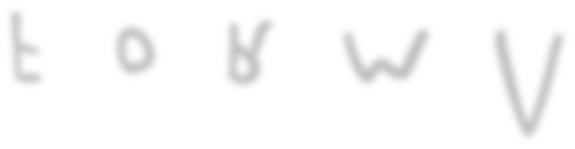-2025.3.14-
竹製コンポストと竹柵づくりワークショップ
ミライマのお向かいの竹林の竹を使って、竹製コンポストと竹柵作りをしてみました。参加者は8名です。
竹細工の趣味をもつ強力な助っ人、高橋さんがきてくださったおかげで、まずは竹の見分け方、切り倒し方、枝の落とし方、割り方、そして大事な刃物の使い方からシュロ縄のくくり方までを教えていただくことができました。基本がわかると竹との距離が近くなりますね。
みんな体験してみましたが、すぐにコツをつかめる人もいれば、道具使いに慣れていないと苦戦する人もいます。人それぞれのところはあるものの、竹の割れる音の響きが思った以上なのと、竹が真っ直ぐに割れる気持ちよさはみなさん共通して感じられたかなと思います。
手慣れた高橋さんはシュロ縄で割った竹を男結びしていきます。結び方は慣れたら簡単とおっしゃいますが、これがなかなか難しい。動画に撮って何度もやってみないとすぐ忘れてしまいそうです。
この日の竹柵は試作なのですが、竹林に入るところから始まってなんとか柵の形ができました。作業場としてお借りしたお向かいのカフェ弄月庵さんの駐車場に仮の柵ができました。



本物の竹柵はやっぱりきれいですね。磨くときれいな竹色になりそうです。竹柵の耐久年数は3年から5年ほどらしいですが、5年で作り直す必要があるということをどう捉えられるでしょう。
そして、竹を切って、割って、縄で結ぶという「手間」。
目の前に資材として使える竹があって、竹林整備をしたいと思っている所有者さんがいます。朽ちても自然に還ります。使わない理由を探すなら「手間」。さて、この手間=時間とも捉えられそうですが、それをどう確保して楽しみましょう、、、悩ましいところです。
というところで予定時間のお昼がすぎて1日目は終わりました。作業の後の一服に、お茶の先生でもある高橋さんにお茶をたてていただきました。お茶をいただきながらみんなで話す。とてもよい時間でした。


翌日は、竹製落ち葉コンポストを作りました。この日はみなさんにお知らせすることなく2人で作業です。切り出してきた竹を畑で組み立てていると、前日に竹柵の試作を一緒にした青のたすきの理恵さんや弄月庵のみわちゃんが、様子をのぞきにきてくれました。
早くカタチにしたい気持ちが先行しアバウトさいっぱいな感じに引きづられたので、設計者テルさんとしては不本意な完成形らしいです(笑)
「真っ直ぐじゃないやん左右も上下も。畑のコンポスト(堆肥置場)やしいいけどなぁ」
思うようなものではないかもしれませんが、なんとかカタチになった竹製のコンポストを畑に置くことができ、落ち葉や刈り取った草を堆肥にする置き場所ができました。


竹がとても身近になったので、野菜の支柱も竹でできそうです。竹林が近くにある方は参考になればと思います。