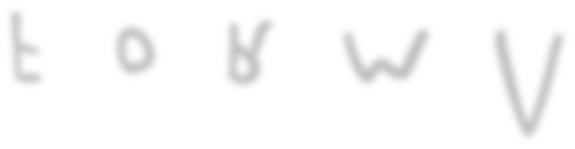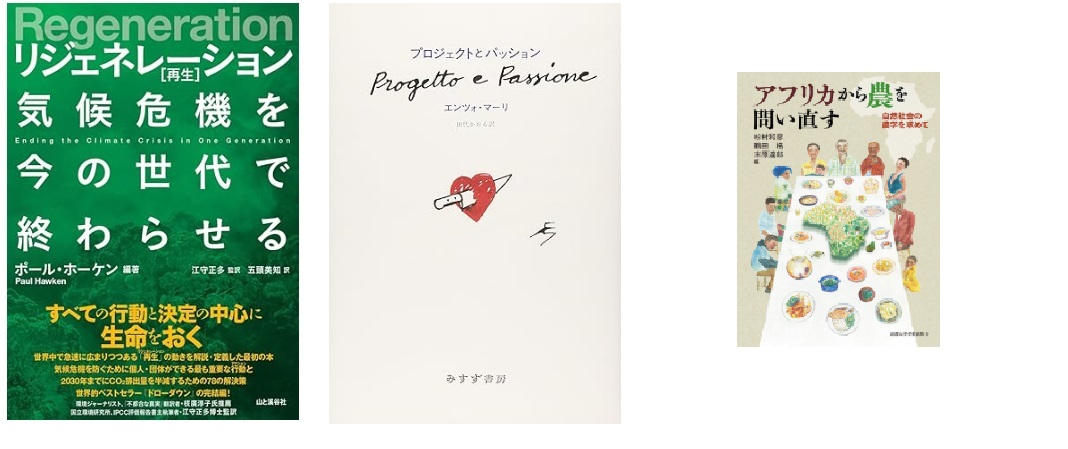category
-2025.3.1-
設計の自由度について
「自由設計!」と明記されている住宅の広告があります。
建売住宅、注文住宅、自由設計住宅と様々ありますが、業界の自由設計の定義というものは無いようです。自由設計といっても間取りや素材の色柄等、自由なところは限定的で、それ以外は決められていることも多いようです。

FORMAのような設計事務所は、限定的に自由というところは少ないと思いますが、それも事務所により異なります。FORMAの場合は以下の点について自由に考えることができます。
・間取(平面計画)
パブリック、パーソナルな各スペースの平面計画、敷地に対する配置計画
・空間の構成
各階ごとのスペースと上下階をつなぐ吹抜や階段の立体構成と配置
・外観のデザイン
風景や景観に配慮、地域の文脈を把握したうえでの外観デザイン、仕上げ
・構造
木造、鉄骨、鉄筋コンクリート造、又は混構造
・断熱、気密工法
外断熱、付加断熱+充填断熱、充填断熱工法と仕様断熱材の種別
・使う素材や仕上げ
使用部材の一切、構造材、下地材、面材、仕上げ材すべての素材
・住宅設備の選択肢
浴室、洗面、キッチン、トイレ、浄水器、電気設備、給水排水設備、換気設備(一種.三種)、エアコン種別 設計して造作とすることも可能
・スマートテクノロジー技術
IOT、HEMS、V2H(Vehicle to Home)等の設置
・再生エネルギー技術
太陽光発電、太陽熱利用、風力、水力、バイオマス等
・将来への備え
がけ地、水害浸水地域時の被害軽減措置、レジリエンス性を高める備え
家を設計するには様々な条件(法律、環境、予算、要望)があります。その中で思考、検討、意思決定をしながら進めていくわけですが、お施主さんがすべてを決める必要があるという意味ではありません。
こだわりたい、選択したい、一緒に考えたいと思うところをお伝えいただければ、プロではないお施主さんに、わからないことまで決めてくださいと言うことはありません。
設計者は、お施主さんとの対話の中から得た想いを元にし、最適と考えるものをご提案します。提案させていただく内容については、提案理由の説明、共有、合意の上で次の段階へ進みます。
建築工事費ついて。
自由設計と明記されていても範囲限定になっている理由の一つはコストです。依然として工事費の上昇が継続しているような状況において、当然コスト感を意識した設計を求められることになります。
コストを抑える手法
・部材の標準化 モジュールの統一、柱、梁寸法を揃える
・流通が多く一般に使われている素材
・湿式仕上げより乾式仕上
・特注商品ではなく既製寸法で構成
・外皮面積を最小に効率的な形状とする
・シンプルなカタチ
・無駄のない平面計画とし床面積を必要以上に大きくしない
・工種を少なくする設計
・工事期間の短縮につながる設計
これらの手法も駆使しつつ、お施主さんの優先順位やこだわりの強弱があります。
それら全体的なバランスを整えていくところにお施主さんの個性、そして設計者の個性がでます。だからこそ、自由に考えられること、言い換えると自由設計が家の魅力につながるのだろうと思います。