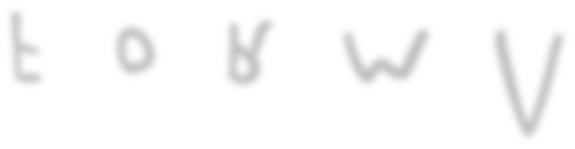category
-2025.4.4-
昔の知恵で今をつくる、竹とともにある暮らしのヒント
竹で小屋を作るワークショップに参加
先日、「民具バンク」主催のワークショップに参加し、竹を使って建物を作る方法を学んできました。
以前から放置された竹林があることが気になっていて、家や暮らしに竹をうまく取り入れる方法を模索していたので、今回のワークショップは絶好の機会!と期待に胸を膨らませての参加です。
タイ山岳民族・アカ族に学ぶ、竹の建築技術
ワークショップでは、タイ北部に暮らす山岳民族「アカ族」の建築技術をベースに学びました。彼らは竹を主材料として、必要なときにすぐ家を建てることができます。これは戦乱や移動の多い生活の中で育まれた、合理的で強くしなやかな知恵です。
この技術を現代日本でも活かせるのではないかという主催者の思いから、3日間の小屋づくりワークショップが開催されました。
鉈(なた)という道具と、心と体の使い方
今回、特に関心を持っていたのは、「竹を板状に加工する技術」です。
が、しかし、板にする前の鉈を使って竹を割る作業が、思っていた以上に奥が深いものでした。
割りたい場所に鉈を正確に振り下ろすのが難しく、最初は全くうまくいきません。力を入れすぎるとズレてしまうし、思ったところに当たらないのです。

割れないとなると、さらに「うまく割ろう」という意識が強くなりそうになりますが、ここで、合気道と同じかもしれないと気がつくことになりました。
- 狙いすぎず
- 一点に集中し
- 鉈の重みを感じながら自然に落とす
このイメージで作業をすると驚くほどうまくいきました。最後には、ほぼ狙った場所に鉈を振り下ろせるようになり、道具と体がつながる感覚が心地よかったです。
合気道の「心と体の使い方」は、日常のあらゆる場面に活かせるのです。
竹の小屋が完成!
3日間かけて完成したのが、こちらの竹の小屋。
軽やかでしなやかな竹が組み合わさって想像以上にしっかりとした構造。見た目も美しく、自然の素材そのものが持つ魅力を実感します。

竹という素材の可能性
竹は成長が非常に早く、しっかりした構造材にもなります。古くから日本でも、稲掛けの支柱や土壁の下地、竹籠、箒、炭など、暮らしのあらゆる場面で使われてきました。
民具だけでなく、建築の部材としても大きな可能性を秘めています。種類によっては、引張強度が鉄筋の1/2〜同等という材種もあるようで、たとえば「竹筋コンクリート」や「竹下地の土塀」なども、十分に実現可能なアイデアです。
もちろん、竹を構造材として使うには建築基準法などのハードルがありますが、仮設や簡易な建築物であれば、柔軟に応用することもできます。
そういった「制度と実践のあいだ」を探っていくのも面白さのひとつです。
そして何より、地域で手に入る身近な素材であることが魅力です。輸送エネルギーがかからないという点でも、サステイナブルな素材と言えるでしょう。
身近な暮らしに活かす竹
試しに、竹を使って柵やコンポストの枠も作ってみました。


加工の仕方や、縄の結び方など、昔ながらの技術は今も活かすことができ、「建築」としても「暮らしの道具」としても、もっと自由に、もっと身近に使える素材だと感じています。
竹はただの雑草でも、ただの和風素材でもなく、「未来の暮らしをつくる素材」として、まだまだたくさんの可能性を秘めています。今後も、暮らしの中で竹をどう使いこなせるか、いろいろ試してみたいと思います。